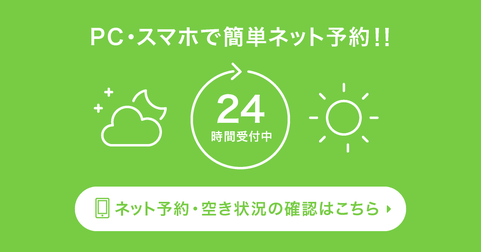新規連載!修士論文から見えた10年も、今回で4回目。
9月も中旬になりまして、修論の最終提出が近づいてきています。
先週は、学位授与式に参加して思わず泣いてしまいました。
ブログシリーズ配信中は、隙間時間を狙って外出するわけにはいかず、さすがに静かに過ごしていたというわけで今回の画像は、8月に郡上おどりに行った時の画像も共に配信してゆきます。
夏の余韻に浸っていただきならが、読んでいただければ幸いです。
前回のブログは、こちら↓
第3回:「教材がない!手探りで生まれた工夫」
紙の教材から始まった試み

当初、子どもたちに使っていたのは手作りのカードや紙芝居のような教材でした。
厚紙にイラストを描き、単語を貼り付け、活動のたびに持ち運びながら工夫して使っていました。
紙ならではの温かみがある一方で、破れたり、紛失したり、子どもによっては扱いづらいという課題もありました。
現在では、すでに破損して現物すら残っていない教材もあります。そうした「痕跡のなさ」もまた、当時のリアルを物語っています。
中でも、動物カードと数字カードは繰り返し使うことで子どもたちの反応が大きく変化する「定番教材」となりました。
言葉とイメージが結びつく瞬間を目の当たりにし、「やはりこのテーマは効果がある」と確信したのを覚えています。
効果的だった教材の一例を以下に、掲載します。

デジタル化への一歩
そうした中で「紙の限界をどう超えるか?」という問いが生まれました。
パソコン上でカードを作成し、印刷だけでなく画面上でも見せられるようにしたのが、私にとって最初のデジタル教材づくりでした。
画像や文字を組み合わせることで、視覚的にわかりやすく整理でき、子どもたちの反応も良くなっていきました。
2019年ごろからは、デジタルとアナログを組み合わせた学習を考えていました。
しかし、ネット環境が整っている家庭ばかりではなく、また市販DVDを利用するにも著作権の問題がつきまとい、完全な移行は困難でした。
そのため、しばらくはアナログ教材を使い続け、対面でのグループレッスンを軸に活動を続けていました。

オンデマンド動画という新たな挑戦
転機となったのは、2020年の新型コロナです。
対面での活動が難しくなり、「これまでの方法を続けることはできない」と強く感じました。
そこで、これまで使っていた紙教材をPDF化し、保護者に配布する方法を取りました。
ここで重要なのは、単なる教材のデータ化ではなく、長年の対面指導やカリキュラム開発を基盤としていたからこそ実現できた方法だったということです。
その流れの中で、絵本の読み聞かせや歌に合わせた「短い動画」を作るようになりました。
数分程度の映像にすると、家庭でも繰り返し使える「小さな教材」になることに気づいたのです。
この試みが、後に修士論文の研究テーマである「オンデマンド教材開発」へとつながっていきました。

紙とデジタルをつなぐ発想
重要だったのは、紙とデジタルを「どちらか一方」ではなく「組み合わせて使う」ことでした。
子どもたちが実際に触って遊べるカードと、家庭でも繰り返し視聴できる動画やPDF。
それぞれの良さを補い合うことで、学びの幅が大きく広がることを実感しました。
次回予告
第5回:「保護者との対話が支えになった日々」
(教材づくりを続けるなかで、保護者の声がいかに大きな支えになったかを紹介します)