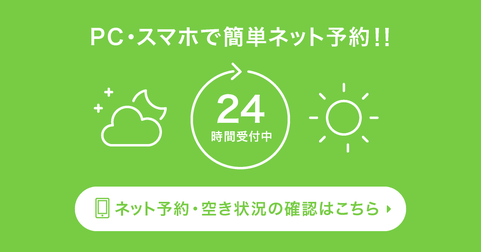子どもの成長と学びの変化
中国語学習を幼児期から始めた子どもたちも、成長とともに「壁」にぶつかる瞬間があります。
最初は歌やリズムで楽しく続けていたのに、小学校に上がると学習への姿勢が変わり、集中が続かなくなることがありました。
続けたくても続けられない現実
さらに現実的な壁も大きなものでした。
乳児や幼児は体調不良や感染症にかかりやすく、保護者自身も子どもから病気をもらって参加が難しくなることがしばしばありました。
希少な活動だったため、市外や県外から通う家庭も多く、距離や交通の負担も大きな課題でした。
また、活動日は土曜日だったため、仕事との両立が難しい保護者も少なくありませんでした。
「大事な幼児期に学ばせたい」という思いはあっても、現実には続けたくても続けられない家庭が多く、メンバーが安定せず、活動回数を十分に確保できない時期が何度もありました。
その一方で、実は同時進行で岐阜県図書館においても、外国語絵本の読み聞かせ活動を担当していました。
限られた時間・不安定な参加状況のなかでも、図書館という公共の場で新しい挑戦を続けていたことは、大きな励みとなり、後の教材研究にもつながっていきます。

こうした課題は数年にわたり続き、私自身も試行錯誤を重ねました。
グループ学習の形を模索しつつ、「オンラインでのレッスンができないか?」と考えたこともありました。
しかし当時は2020年以前であり、オンライン学習はまだ一般的な選択肢ではなく、まして幼児に適用するのは難しいと誰もが考えていた時代でした。
まさかこの課題への試行錯誤が、後に自分の研究テーマへとつながるとは、その時は夢にも思っていませんでした。
仲間との挑戦
その試みのひとつが、絵本の読み聞かせに音楽を取り入れることでした。
ここで大きな力となったのが、パートナーであるR(音楽家)です。
Rは、絵本の世界観を引き立てるBGMを担当してくれ、子どもたちが物語と音の両面から言葉を楽しめる環境を作ることができました。
さらに、通訳経験の豊富なTにも協力を依頼し、地域の子どもたちや保護者と共に小さなサークルを立ち上げました。
そこでの実践は、教室の枠を超えた学びの場となり、教材開発のアイデアの宝庫にもなりました。
学びの壁を越える工夫
壁にぶつかっても学びをあきらめず、環境を工夫することで思いがけない新しい形が生まれる。
その実感こそが、私にとって教育実践の宝物となり、やがて修士論文の根幹を支える学びへと発展していきました。

今回は、8月の終わりに滋賀県米原市醒ヶ井宿へ観光してきた画像を掲載させていただき、夏の終わりを楽しんでいただければと思い共有させていただきました。
梅花藻(ばいがも)の季節ということで、初めて散策してみました・・・ 真夏の暑い日に訪れましたが、醒ヶ井の水は真逆で冷水・・・頭から水を被らせてもらいましたが、キンキンするほど冷たくて一気に涼しくなるなど五感が刺激されました。
みなさんは、暑いながらも素敵な思い出はできましたか?
次回予告
第3回:「第3回:教材がない!手探りで生まれた工夫開発の試行錯誤」
(歌・絵本・ゲーム…現場で試した工夫の数々について紹介します)