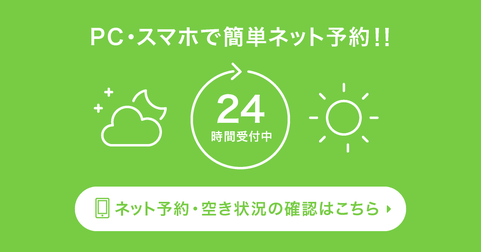基本の挨拶に集中したレッスン
小学1年生のYさんとのレッスンでは、この日はあえて基本の挨拶だけに集中しました。
こんにちは、おはようございます、こんばんは、おやすみなさい、ありがとう、どういたしまして。
まずは日本語で挨拶をしてから、中国語に置き換える練習です。
この「置き換え」は、学習者にとってフィルター(翻訳)を通す作業であり、気持ちよくスムーズにそのフィルターをかけることが大切です。
ただ、この学習は面白さと同時に難しさも伴います。

今回は、6月初旬に開催した御神木祭の様子、及び中津川観光の画像とともにブログを配信します。
20年に1度と言う貴重なイベントに参加者、本当に感動でした。話は戻しますね。
指導者の役割は「気分良くフィルターをかける」
指導者の役割は、学習者がこのフィルターを気分良くかけられるように仕掛けて、応援することだけです。
そうでなければ、今は語学学習アプリで自宅学習することも可能です(もちろん、その場合は自己管理能力が問われますが)。
だからこそ、対面や双方向のやり取りでは、学習者が安心して挑戦できる環境づくりが欠かせません。

学びの中で見つけた「言葉を切り替えるきっかけ」
かおり先生は、この「言葉を切り替えるきっかけ」の意味を、これまでの学びを通して深く考えるようになりました。
どんなに優れた学習者でも、言葉を瞬時に変換する力は、積み重ねと練習なしには身につきません。もちろん、かおり先生でも同じことです。
語学の天才はごく稀な存在
歴史を振り返っても、語学に特別な才能を持つ人はごく一部です。
18世紀のプロイセン国王・フリードリヒ2世は、5か国語を操ったといわれていますが、このような例はごく稀です。
現代でも、皇后雅子さまや愛子さまのように、幼い頃から複数言語に親しんだ方々はごく限られています。昭和の時代と比較すれば、格段に増えたかもしれませんがそれでも、多くの人にとって語学は、忘れたり思い出したりを繰り返す中で、時間をかけて身につけていくものです。

「忘れる」ことを前提にした学びの姿勢
特に低学年のうちは、保護者の方が「もっとできるはず」と感じることもあるでしょう。
けれど、背伸びよりも、忘れたことを一緒に振り返り、どうすれば思い出せるかを考えるプロセスこそが、本当の定着につながります。
かおり先生は今、長いような短いような?2年半の大学院での学びの期間も一区切りを迎えようとしています。
この節目に、Yさんとのレッスンを通して、基礎を見直す時間の大切さを改めて感じてたんです。
これは、学びの現場に立つ私自身にとっても、大きな原点の確認になった案件だなと思って、この場でお伝えしました。

まとめ
本日は8月12日。お盆までわずかとなりました。
暑さは少しピークを越したので、安心ですねと言いたいところですが、国内各地で集中豪雨などに見舞われている地域もあるようですね。
もはや日本は安全とは程遠い国になりましたので、学びのスタイルも「いつでも教室に行ける。」「いつもの仲間がいる」という感覚は少なくなるのかもしれません。特に、夕方の西日は日焼けになりやすいですよね。夏休みではない場合、中国語教室に通われるご家庭も多いとは思いますが、気象によって体へのダメージが老若男女関係なく襲いかかってくるというのが、日常になってさえきたように思います。
デジタル・アナログ学習のメリットデメリットについては、これまでのブログでも時々お伝えしていますが、改めて言語化することで、共通理解できらた幸いです。