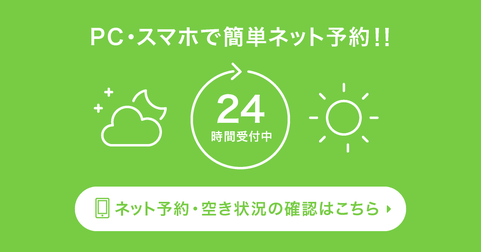夏休みが始まりましたね。
前回のブログでは、暑いと連呼しておりました。
8月3日(日)・・今日も、暑いです。
都会とはまた違って、盆地である岐阜ならではの暑さと言うものがあり、活動的に何かやろうという気持ちになかなかなりにくいですね。
皆さんのお住まいの場所でも、暑い日が続いていますか?
とにかく無理をせず、ある程度自分を甘やかしても良いのではないか?と思う今日この頃です。
今回は、少し前の6月に長野に行った時にしか撮影できない、りんごの実(赤ちゃん)と岐阜で撮影した自然風景を投稿しつつ、ブログを書いていきますね。

「孟母三遷」という故事をご存知でしょうか?
子どもにより良い学びの環境を与えるため、孟子の母が三度も引っ越したという、教育の象徴ともいえるお話です。
実はこの故事も、司馬遷の『史記』に記されています。
昨年の夏、その『史記』を漢文原文で購読するという、挑戦的な自由科目に取り組みました。電子辞書は禁止。紙の辞書を片手に、たった一行を読み解くのに何十分もかかる日々でした。
それでも、不思議と途中でやめようとは思いませんでした。
司馬遷が、屈辱的な刑罰を受けながらも命を削って書き上げた『史記』。その文字には、「学ぶとは何か」を問う深い覚悟が宿っていました。
そして、気づいたのです。
中国語を学ばせたいと願い、学びの場を選び、環境を整える——そんな保護者の姿こそが、まさに「孟母三遷」の実践ではないかと。

大学院での学びも、残すところあとわずかとなりました。
けれど、この『史記』との出会いがもたらした「学びの重み」や、「言葉を受け継ぐ」という行為の意味は、これからも自分の教育実践に深く刻まれ続けていくと思います。
次回のブログでは・・・
現在、受講中の生徒の保護者の皆さまの中にも、まさにこの「孟母三遷」を実践されている方が多くいらっしゃいます。
夏休み真っただ中の今、どの生徒もそれぞれのペースで、自分に合った中国語の学習スタイルを模索し、取り組んでいる姿がとても印象的です。
中学受験とのバランスを取りながら、心身の健康にも配慮しつつ進めるレッスン。
一人ひとりに寄り添うからこそ見えてくる「その子らしい学び」のかたちがあります。

その中のひとり、4月から小学1年生になったYさんも、まさに今、小さな変化と自信を積み重ねているところです。
これまでブログではあまり紹介してきませんでしたが、
「夏休みに少しでも上手になった!」「会話ができるようになってきた!」と感じてもらえるように、彼女に合わせたカリキュラムを楽しみながら進めています。
次回は、そんなYさんの様子や、具体的なレッスンの工夫について少しお話ししたいと思います。